人は楽しんで生きなければいけない。いや人には楽しんで生きる義務があるのだ、ということを村上龍の作品から教えられた。受験戦争に巻き込まれ、それが終わると競争社会に翻弄され、職場の人間関係に振り回されながら過ごしていた日々が村上龍の小説やエッセイに出会って少しづつ変わっていった。
人はどうせ苦しむ存在なのだから、わざわざ買って出てまで苦しむ必要はないと諭してくれたのかもしれない。
新宿の紀伊國屋書店で偶然にも村上龍がサイン会をしているのに出くわしたことがある。それで私は会場にまだ現れていない村上龍を書棚の影から待ち伏せることにしたのだった。やがて黒のタートルネックのセーターの上にカシミヤ製であろう濃いネイビーのジャケットを羽織りサングラスをした本人が現れた。彼はサイン用の席に着くと、周囲のスタッフに何か耳打ちをするように指示を出した後、手元にあるサイン用のマジックペンで何やら試し書きを始めた。そして「サイン用に用意されたマジックのインクの出が悪いわけないか」というようにキャップを戻しながら薄く苦笑いをしたのだった。それら眼前で起こった一連の「生」の村上龍の有り様に私は惚れ込んでしまったのである。
作家がこんなに格好いいってありなのか?
その直後である。私の方向へ一瞬村上龍が目を向けた。無論私がそこにいることを村上龍は知らないはずだし私を見るわけがない。
彼の眼光がキラリと怪しく光った。
獲物を狙うが如くサングラスの奥のその瞳が確かに光ったのだ。一瞬私は狩られてしまうのではないかと思った。
きっと村上龍ライオンはその鋭い眼光で目の前の風景の中から小説のテーマや題材になりそうな「情報」を獲物として捕捉し狩りをしながら生きているのだろうな、と思った。
「料理小説集」はグルメ本ではなくあくまで小説集である。京都のすっぽんやらウェルク貝、スルビンというナマズ、フェジョアーダと世界中の聞いたこともない美しい料理達が次々と紹介され登場人物達の人生を美しく彩りながら優しく寄り添っていく。
どの編の主人公も金があり遊び人で極めて知的だがスノッブではない。そして女性によくモテる。お嬢様からヤンチャなギャルまであらゆるタイプの女性から最高度に洗練されたスタイルで誘惑されるのである。そして主人公は美しい料理達に対するのと同様に最上の敬意をもってそれぞれの女性達に相対するのであった。
多分村上龍本人の実体験が混じっているのに違いないと匂わせる表現の仕方がいちいち憎い。
格好よさにはスタイルが必要なのだということを教えてくれる短編集である。
「走れ!タカハシ」には、小説を読んで腹を抱えて笑うという体験を初めてさせられた。村上龍の作品にしては珍しく、世界を根底からひっくり返すような筋書きの作品群から一転して、まるで一流のドタバタコントを見ているような短編集である。だが、この小説の極め付きは「あとがき」にあると思う。最上のお笑いコントの直後に、現代を覆う暗さを見つめた嘆き節が続くのだ。その対比にまたしてもヤラれてしまうのである。
落ち込むことの多い日々の中励まされたいなら「55歳からのハローライフ」を読むのがいい。散々破天荒な生き方をする主人公を描き続けた村上龍が、我々一塊の庶民達の生活を優しい眼差しで見つめ描いた切なくも救いのある物語集である。これを読んで村上龍という作家の懐の奥深さにしみじみと感じ入った。従来の作品とのコントラストを感じさせながらこういった作品を書けるあたりが村上龍という作家の本質であり魅力なのだと思う。
物語のいくつかは「救いのある飲み物」がモチーフになっている。主人公が日々の厳しい暮らしの中ペットボトルに詰まった外国産の上質な水を飲むことを自らの救いとし、それを友人にも勧め共に救われる。その一編を読んでしばらくの間、私も心が苦しくなった時お酒ではなくペットボトルのお茶を一口飲むことで救われながら辛い日々を生き延びたのだった。
「オールドテロリスト」は60歳過ぎいや70歳を過ぎてもいやとにかく年老いたら、ますますもって人は人生を楽しむ義務があるのだと感じさせてくれる年寄り達が主役のスペクタクルロマンである。
この小説がいいたいのは、年老いたら残りの人生何をしてもいいということではないだろう。老いてから楽しむには、若いうちに知的な蓄えを十分にしておく必要があると教えてくれるのだ。何が自分にとって本当に楽しいことなのかを若いうちに考え抜いておかなければ、年老いてからの冒険はできない。
もっと直接的に村上龍自身の魅力に触れたいなら「おしゃれと無縁に生きる」のようなエッセイ集を読むのがいい。
女性にモテたかったら、夥しい量のエッセイに散りばめられた彼の哲学や生き方を知り、そして真似ればよい。
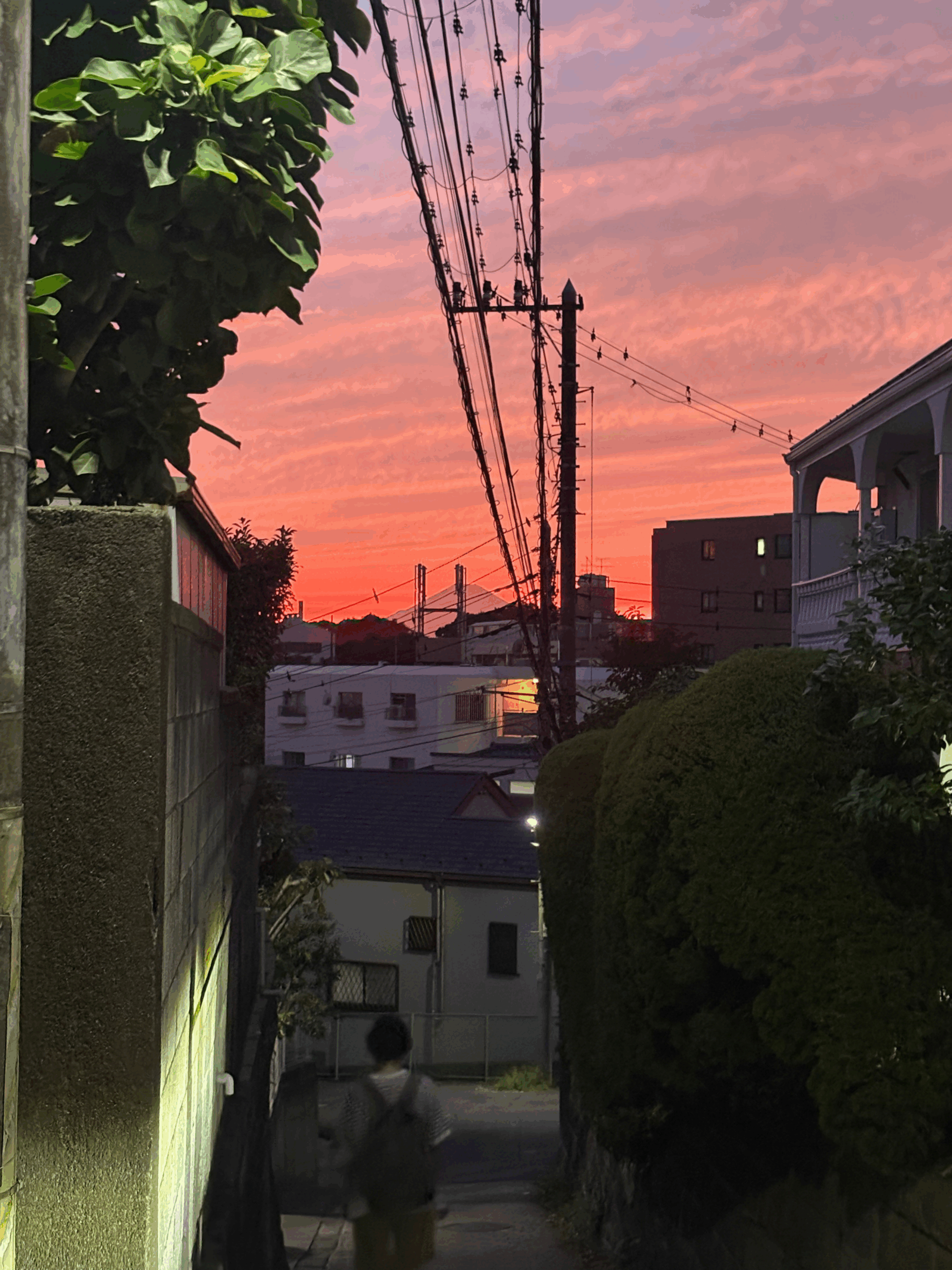


コメント